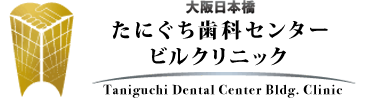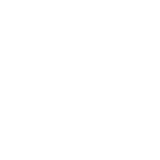インフルエンザや風邪の対策について
2024年2月16日
皆さんこんにちは😀
寒い日が続いていますが、体調など崩されていないでしょうか?
この時期になると毎年流行るのが、インフルエンザです。
皆さん、インフルエンザや風邪の対策はきちんと行っていますか?
実は手洗い、うがい、ワクチン接種以外にも予防に有効と言われているのが、口腔ケアなんです🦷
口腔内の虫歯菌や、歯周病菌を含む細菌が、食べカスなどを餌としてたんぱく質分解酵素を出し喉の粘膜を荒らすため、
荒れた粘膜にインフルエンザなどのウイルスが付着しやすくなり、発症しやすいと言われています。
口腔ケアとして、毎日の歯磨きや定期的なクリーニングがインフルエンザや風邪の対策にとても重要になってきます!
適切な歯みがき、定期検診などの口腔ケアで予防をしていきましょう✨
新年のご挨拶
2024年1月9日
新年あけましておめでとうございます✨
年末年始皆様はどのようにお過ごしでしたでしょうか?
心身ともにリセットできましたでしょうか?
スタッフ一同、ご来院お待ちしております🦷
歯ぎしりや食いしばりによる影響
2023年11月28日
皆さんこんにちは😀
今日は歯ぎしりや食いしばりについてお話します。
歯ぎしりや食いしばりをしていると常に咬筋に力が加わり、ますます歯や歯周組織、顎関節に負担がかかってしまいます。
これが歯のすり減りや知覚過敏、被せ物が取れたり欠けてしまう原因に繋がっていきます。ひどい人はインプラントが折れてしまうこともあります😨
さらに、歯ぎしりの時に使われる多くの筋肉は首や肩へと繋がっており、顎の筋肉だけの問題ではないことが多いんです。
歯ぎしりをすることによって周囲の筋肉が緊張し筋肉がこわばってしまう為、首や肩が凝りやすくなってしまうのです。
これらは、咬筋ボツリヌス治療を行うことで咬筋の力が弱くなり、顎が疲れなくなったり、頭痛や肩こりの解消にも繋がります!
歯ぎしりをしなくなったという方もいらっしゃいます。
また、当院ではマウスピース治療も行っております。
歯ぎしりや食いしばりなどでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください!
スタッフ一同お待ちしております🦷
お子様の歯並び(すきっ歯)について
2023年10月6日
こんにちは!
今日は子どもの歯並びについてお話します。
保護者のみなさんは、「うちの子、すきっ歯・・・?」と不安に思った経験がある方はいらっしゃいませんか?
ご安心ください、ほとんどの場合それは正常です👌🏻👌🏻
乳歯は隣の歯との間に隙間があることが本来では正常なのです。
子どもは10歳になると、お口の中に乳歯と永久歯が混在している状態になります。
この状態を、混合歯列期(こんごうしれつき)と言って、歯の高さが違ったり、部分的に歯ぐきがかぶっていたりと歯磨きの難しい時期になります。
混合歯列期の特徴はいわゆるすきっ歯というものです。
歯と歯のすき間があることで、乳歯より大きい永久歯が生えてくるためのスペースが確保できるのです。
乳歯の段階で歯と歯のすき間がないと、永久歯の生えてくるスペースが足りなくなり
歯並びが悪くなってしまいます💦
しかし、スペースが十分にあったとしても、日常の口腔習癖により歯並びが悪くなってしまうこともあります。
・指しゃぶり(4歳以上の場合)
・爪を噛む
・お口ぽかん
・口呼吸
・舌を前に出す
・唇を巻き込む
・うつ伏せで寝る
・頬杖
などが例として挙げられます。
これらの習癖をしていることがあれば声をかけて注意してあげるようにしましょう!!
乳歯の時期から、将来的な歯並びの善し悪しの予測は
ある程度つくので定期検診の際にお伝えさせて頂いております💡
スタッフ一同、ご来院をお待ちしております😊
スポーツドリンクの飲みすぎに注意!!
2023年8月9日
皆さんこんにちは😊✨
最近、暑い日が続いてますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
部活動などで毎日運動をしている方も多いかと思います。
運動をするうえで欠かせない水分補給ですが、夏は特にスポーツドリンクをたくさん飲まれる方が多いのではないでしょうか?
しかしスポーツドリンクには意外な落とし穴があるのです!
スポーツドリンクに含まれている糖質の値は砂糖が4~6%と記載されていて、おいしさを出すために多めに糖質が配合されています。
そのため、スポーツドリンクを飲みすぎると知らないうちに虫歯の原因に繋がっていってるんです・・・
虫歯にならないための対策法としては、
・がぶ飲みをしない
・スポーツドリンクを飲むごとにお口をすすいだり、お水をひと口飲む
・キシリトールタブレットを摂取する
などが挙げられるので、ぜひ試してみてください!
スポーツドリンクや水などでしっかり水分補給をして、熱中症にならないよう暑い夏を乗り越えましょう😁
また、何かお困りごとがあれば気軽にご相談ください!
歯茎の検査について
2023年6月30日
こんにちは🥰
皆さんは歯茎をチクチクする検査を受けた事はありますか?
定期的に受診されている方はご存じかと思いますが、この検査は歯周病かどうかを確認する「プロービング検査」と言います。
プロービング検査とは?
プローブという針状の器具を使用し、歯と歯ぐきの間にある歯周ポケットの深さの測定と出血の有無の確認をします。
プローブにはmm単位の目盛りがついており、その目盛りを基準に歯周病の進行状態を調べます。
歯周病の進行度は、下記が目安です。
0~3mm 正常値
4~5mm 初期~中等度歯周病
6~9mm 中等度~重度歯周病
10mm以上 重度の歯周病
また深さだけではなく、プローブを入れたときや外した後の出血を見ます。
すでに炎症が起きている部分をプローブで触り、出血するかを確認しています。
毎日のブラッシングと定期的なお口のメンテナンスを行い歯周病を予防していきましょう🥰✨
歯周病と糖尿病
2023年5月26日
皆さんにんにちは😊✨
今回は、歯周病と糖尿病の関係についてお話していきます。
歯周病は、歯周病菌の感染により歯茎や歯を支える骨に炎症が起きる病気です。日本では成人の約8割が歯周病にかかっていると言われています。
一方、糖尿病は、血糖をコントロールしているインスリンというホルモンがうまく作用しなくなることで、血液中の糖分が多くなってしまう病気です。
実は、歯周病と糖尿病は、お互いに悪影響を及ぼしあっています。
糖尿病の人は、健康な人と比べて歯周病になるリスクが高く、また、歯周病の方が治療によって歯肉が改善するとインスリンが働きやすい状態になって、血糖値が改善する可能性があるという報告があります。
そして、歯周病と糖尿病の予防方法について、やはり1番は早寝早起きや適度な運動、バランスの良い食事といった規則正しい生活習慣が大切です!
さらに、歯科医院への検診を取り入れることでより一層、将来の健康が守られると思います!
お口に問題がないと思われていても、1度ご来院されてみてはいかがでしょうか?
ナイトガードについて
2023年4月14日
皆さんこんにちは🥰✨
朝起きたとき顎が疲れていたり、虫歯ではないのに歯が痛んだ事はありませんか?
それは、就寝中の歯ぎしり・食いしばりが原因かもしれません。
睡眠中の歯軋り・食いしばりは無意識に行われるため、自分で気づいて止めることが難しいと言われています💦
これらの症状としては
・歯が削れる
・詰め物や被せ物が取れる、割れる
・知覚過敏
・歯周病の悪化
・顎関節症
・肩こりや頭痛
歯や歯以外に多くの影響を与えてしまいます😢
そこで有効とされているのが、就寝時に使用するナイトガードや咬筋ボツリヌス治療です。
ナイトガードは装着する事によって歯列全体に歯ぎしりの力を分散させ、1本にかかる負担を軽減する事ができます!
保険適用で作成することができますので、歯ぎしりや食いしばりでお悩みの方や気になる方は
お気軽にご相談下さいね🌸
また当院では、定期検診の際にナイトガードの確認や超音波洗浄させて頂いてるのでご来院の際お持ち下さい✨
咬筋ボツリヌス治療は、噛む力そのものを弱める治療です。
こちらも当院で治療可能なので、気になる方はぜひお問い合わせください😊
マスクと口呼吸
2023年3月4日
皆さんこんにちは😎✨
コロナ禍でまだまだ大変な時期が続いていますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?
すっかりマスク生活にも慣れましたね😷
今回は、そんなマスク生活が及ぼす、お口の中への影響についてお話しします。
普段私たちは鼻呼吸をしていますが、長時間マスクをしていると、息苦しさから口呼吸になりやすくなります。
口呼吸は、こんな悪影響をもたらします😥
①虫歯や歯周病の進行、口臭の原因になる
お口が開いた状態が続くことで、お口の中が乾燥し、唾液の量が減ってしまうため、虫歯・歯周病などになりやすく、口臭の原因にもなります。
②風邪を引きやすくなる
お口から直接ウイルスが入ることで、風邪を引きやすくなり免疫力の低下に繋がります。
③歯並びが悪くなる原因になる
お口周りの筋肉や表情を作る筋肉、舌などの筋肉を鍛えることができず歯並びに影響を与えます。
また、顎の成長の妨げの原因にもなります。
口呼吸は無意識の場合が多いです。お口や身体の健康のためにも、普段から鼻呼吸を意識して過ごしましょう!
当院では、まだまだコロナ対策をしっかりしておりますので、安心してご来院いただけます!
お待ちしております😊
歯ブラシの交換の目安について
2023年1月10日
皆さんこんにちは😊✨
今回は「歯ブラシの交換の目安」についてお話しします。
皆さんの歯ブラシの交換頻度はどのくらいでしょうか?
1日3回毎食後、歯磨きをした場合、歯ブラシの寿命は約1か月と言われています。
同じ歯ブラシをずっと使い続けるとどうなる❓
・虫歯や歯周病になりやすくなる
→毛先の開いた歯ブラシでは、汚れを十分に落としきることができず、汚れが残ったままになってしまいます。
その結果、虫歯や歯周病になりやすくなります。
・歯茎や歯を傷つけやすくなる
→新しい歯ブラシの毛先には弾力性があります。
毛先が広がり古くなるとその弾力性が失われ、歯茎や歯を傷つけてしまいます。
・細菌が増殖する
→口腔内には常在菌が存在しています。歯を磨くことによって歯ブラシの毛先には細菌がたくさん付着し、使い続けているうちに繁殖していきます。
古くなった歯ブラシには特に菌が多く、適切な保管をしていてもヘッドの部分は汚れていってしまいます。
3週間ほど使い続けると細菌の数はおよそ100万個になり、1か月以上使った歯ブラシはトイレの水の約80倍の数の細菌になるとも言われています💦
毛先の部分に水分が残っていることによって、カビや雑菌が繁殖してしまいます😫
使い終わったらしっかりと水洗し乾燥させ、清潔な場所に保管するようにしましょう!
歯ブラシの交換の目安は1か月ですが、歯ブラシの毛先が開いていては汚れの除去率が悪くなってしまいますので、気付いたら交換するようにしてください👍
あまり早く歯ブラシの毛先が広がってしまう方は、もしかすると歯ブラシの圧が強すぎる可能性があるので、今一度見直してみて下さい!
何か分からないことがあれば、お気軽にご相談おまちしております😊